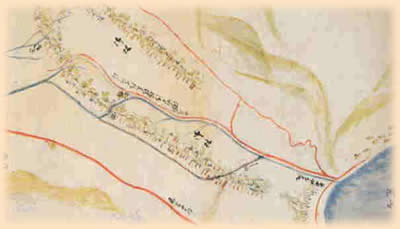梁 尻 堰(やなじりせき)
延宝2年(1674)8月2日より山中湖と忍ヶ湖の間の丸尾(溶岩)を開削工事に着手した。
この延宝2年には暮地の今井堰(今堰)工事も着工されており、郡内の領主秋元喬知が、寛文検地による生産力の把握と伴って、その生産力を高める条件整備の一つとして、水利工事に積極的になっていた時期にあたる。
この梁尻からの導水工事にも、今井堰工事の奉行今井半兵衛がまた奉行として差配した。
区間の長さは12町余(約1,400メートル)、これを1年に4町ずつ仕上げる計画であったという。
この工事には、現富士吉田市域の上吉田村・下吉田村・新屋村・松山村・新倉村・大見村・小明見村の七ヶ村が中心となって人足を出し、これに阿曽谷と呼ばれる富士北麓の村々や、桂谷と呼ばれる桂川沿いの村々からも人足が出て、完成までに延6千人を要したという。
こうして桂川は、山中湖から導水されて北西へ流れ、内野村の湧水や忍草村の「忍野八海」などの湧水を加え、大堰で二流に分れる。うち一流は北東に流れ、こちらが本流にあたるが、その流れは三流に分れる。
うち東寄りの流路は大明見・小明見への用水路となり、西寄りの流路は下吉田の用水路となっている。真中の流れは桂川本流としてさらに下流の村々を潤す。一方、大堰から北西に流れていく一流は、福地用水となる。
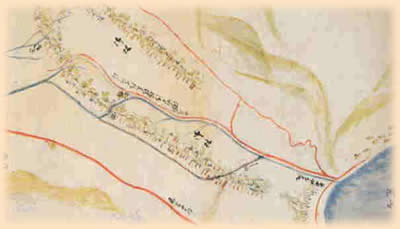
- 【詳しく知りたい人】
- 谷村藩主秋元公拾遺 1989 窪田薫
秋元家甲州郡内治績考(館林本準拠校訂版)1994 秋元藩政研究会
![]()
![]()