
円 通 院(えんづういん)
 曹洞宗大慈山円通院という。本尊は釈迦牟尼仏で、開基は、梅岩全芳居士、開山は長生寺三世融山宗祝禅師である。
曹洞宗大慈山円通院という。本尊は釈迦牟尼仏で、開基は、梅岩全芳居士、開山は長生寺三世融山宗祝禅師である。
古くは観音を本尊として円通庵といい、応仁元年(1467)に竹の鼻(都留市駅前付近)に開創されたと伝えられている。
寛永10年(1633)秋元泰朝が谷村城主となった頃、領主の計いで茶園場と呼ばれている現在地へ諸堂を移し円通院と改めた。
- 鐘楼と梵鍾
- 鐘楼は、宝暦元年(1751)に再建されたものだが、梵鐘は秋元喬朝の重臣高山甚五兵衛朝繋が円通院に帰依し、信仰深かった母親の供養のため、33回忌にあたる貞享3年(1686)に寄進したものである。鐘製作にあたった鋳物師は、日光東照宮の家康墓所の宝塔を造立した椎名伊予藤原良寛の手により、鐘銘の記述者は永平寺35世の晃全板撓和尚である。
梵鐘は、市文化財に指定されている。
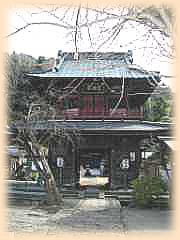 山門覚雄殿
山門覚雄殿- 山門は覚雄殿といい、加賀金沢の大乗寺の愚禅和尚によって、大乗寺の山門大雄殿を偲んで命名されたもので、寛延元年(1748)に造営された。寺は山門の両側に祀ってある阿吽二体の持国天、多聞天に護られている。
- 薬師堂
- 薬師堂は東光院医王堂と呼ばれ、寛永年間谷村城主秋元喬朝が病にかかったときに、侍医上田見徳が良薬をすすめたが治らなかった。
ある夜、夢の中でのお告げにより、一宇を建立して薬師如来を安置したところ、たちまち病が治ったとのことである。
その後、上田見徳に薬師堂の管理が任され、大神宮中腹に祀ってあったが、城主秋元氏が川越に移封するに当って、医師桑貝宗林に引継がれ、また円通院に受けつがれたもので、本尊は秘仏とされ、20年に一度度開張されることになっている。
元坂の石橋
この石橋は、江戸時代から家中川にかけられてあった五石橋の一つで、築造の年代は明らかでないが、長い風雪に耐えた石肌が昔を偲ばせている。石柱の橋脚の上に石の板を置いただけの簡単な工法だが、その強度は大正12年の関東大震災のときも崩れることはなかったといわれている。
昭和になって横幅が狭いため、つぎつぎと取りこわされ、上谷から元坂に通じるところにあったものが、円通院の放生池に復元されている。橋の長さ6.23m,幅1.2mで、昭和50年9月25日市の文化財に指定されている。
- 閻魔堂
- 昭和45年に建立されたもので、この間魔堂には、正福庵(もと円通院の中雀門北にあった)という小さな寺にあった十王尊像が、安置されている。十王尊像の内、「えんまさん」は講談の「肉づきの面」で知られる面作り師源五郎の作といわれ、新宿の大宗寺の 「えんまさん」とともに、江戸時代の名作の一つとして有名であるという。
- 芭蕉句碑
- 円通院境内に芭蕉の句碑がある。
旅人と我名よはれんはつ時雨 芭蕉
10月12日 嵐雪三世居二代六花庵建立
六花庵二世官鼠(かんそ)は嵐雪三世蓼太(りょうた)の門人で芭蕉の顕彰に尽し、各地に芭蕉の句碑を建立している。
- 【詳しく知りたい人】
- 高取堅二 『碑が語る谷村藩士物語』 1997 円通院
郡内研究 第11号「三門・山門の謎 円通院の二天門」高取堅二 2001 都留郷土研究会
甲斐国志 第3巻 仏寺部 1971 雄山閣
都留市寺記(都留市文化財調査資料)1976 都留市教育委員会
芭蕉の谷村流寓と高山麋塒 1981 小林貞夫
![]()
![]()
 曹洞宗大慈山円通院という。本尊は釈迦牟尼仏で、開基は、梅岩全芳居士、開山は長生寺三世融山宗祝禅師である。
曹洞宗大慈山円通院という。本尊は釈迦牟尼仏で、開基は、梅岩全芳居士、開山は長生寺三世融山宗祝禅師である。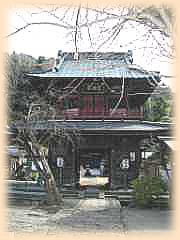 山門覚雄殿
山門覚雄殿