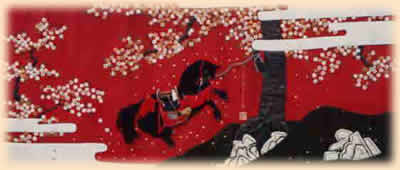鳥文斉藤原栄之(ちょうぶんさいふじわらえいし)
 栄之(1756〜1829)は、本姓細田で、の家は500石取りのれっきとした旗本で、栄之が生まれたとき祖父は勘定奉行であった。
栄之(1756〜1829)は、本姓細田で、の家は500石取りのれっきとした旗本で、栄之が生まれたとき祖父は勘定奉行であった。
初め山伏井戸(現・明治座附近)のち本所割下水に住んだ。天明・寛政の間に活躍し、その気品ある作調は官能的な歌麿に対比されるほどであるといわれる。 系図によると、父時行の妻は境野氏であったが栄之の母は某氏とあって、妾腹の子であったといわれている。
彼自身は西の丸の御小納戸衆の一人で将軍家治に仕えていたが、天明3年(1783)寄合衆に転じた。病弱のためであったという(『古典備考』)。のち寛政元年には家督を譲っている。
栄之の最も早い仕事は木挽町狩野家6代栄川院典信門下として、天明5年の黄表紙であった。
清長全盛のころである。寛政元年衣服等奮移禁止令が出るが、清長風構図「青楼江戸紫・てうじや内ひな鶴」は、紅嫌い(紅色を追放した)を更に進めて、紫絵といったほとんどモノクロめいた境地にあり、これは栄之の創案といわれている。「青楼芸者撰」は、シリーズ中のモデルいつ花・いつとみが、連名で『吉原細見』にのっているのは寛政2、3年で、そのころの制作とされる。
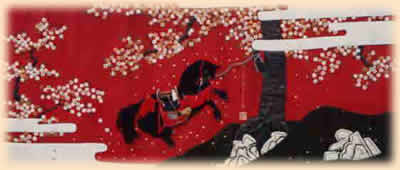
八朔祭仲町屋台後幕「桜に駒」
この「桜に駒」は、美人画を主として描いていた栄之としては特異な画題が用いられている。
この幕の落款には、「鳥文斉藤原栄之之図」とあり、この「栄之図」と署名が用いられるのは寛政後期から淳和年間おそくも文化初年までの間と考えられている。
- 【詳しく知りたい人】
- 小池満紀子「甲州谷村の浮世絵」『浮世絵の現代』 1999 勉誠社
棚本安男「谷村の祭礼 八朔祭」『郡内研究第10号』 2000 都留市郷土研究会
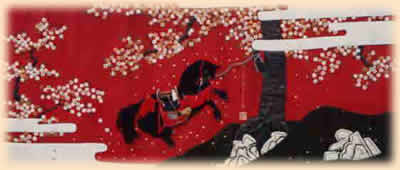
 栄之(1756〜1829)は、本姓細田で、の家は500石取りのれっきとした旗本で、栄之が生まれたとき祖父は勘定奉行であった。
栄之(1756〜1829)は、本姓細田で、の家は500石取りのれっきとした旗本で、栄之が生まれたとき祖父は勘定奉行であった。