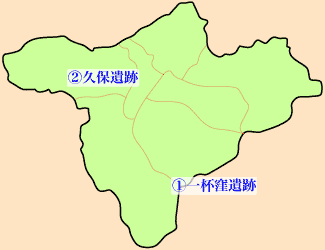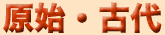
先土器時代(今から1万2千年以前)

約200万年以前の更新世に現世人類が出現し、最初に形成され た人類の文化を旧石器文化、その時代をヨーロッパでは旧石器時代と呼んでいる。
日本では、縄文土器が出現する1万2千年前を先土器時代と称している。市内では、一杯窪遺跡(菅野)、久保遺跡(大幡)が知られている。
- 【詳しく知りたい人】
- 都留市史 通史編 1996 都留市史編集委員会
①一杯窪遺跡 都留市菅野
- 【立 地】
- 道志山地の山懐深い標高900mの北西に張り出した尾根の末端部に位置する。ここは菅野川の源流地であり、傍らの沢には細粒凝灰岩の大小の転石が豊富に認められる。
県道谷村ー道志線の道坂トンネル手前、道路の切り通しにおいて、表土より10m下においてたまたま赤土取りの際発見された。
- 【調 査】
- 昭和53年発掘調査が実施され、2,600点におよぶ、石核、剥片を主体に、斧形石器、削器類が出土した。
石器は、一部のチャートを除くと、細粒凝灰岩に限定され、この岩体が遺跡背後に露出し、前面の原に転石として豊富に存在する。これらから、本遺跡が豊富な石材を得て、石器制作を目的としたキャンプサイトであったことを物語っている。石器が出土した土層から取り出した炭化物の炭素測定をしたところ約32,000年前のものであると報告されている。
- 【詳しく知りたい人】
- 『山梨県史資料編1』1986
都留市史 地史・考古編 1986 都留市史編纂委員会
② 久保遺跡 都留市大幡
昭和42年に、山本寿々雄氏によって宝小学校裏の大幡川の断崖より、細石刃、細石核、柳又型類似の尖頭器が発見された。
- 【詳しく知りたい人】
- 都留市史 地史・考古編 1986 都留市史編纂委員会
山梨県の考古学
![]()
![]()