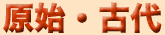
歴史時代
- 【概 説】
- 弥生時代に広まった水稲農耕は、鉄製農具の普及により可耕地が広がり、各地に小国を支配する豪族を台頭させた。さらに戦争により小国が統合され、邪馬台国の卑弥呼のような王が出現し、権力の象徴として古墳の造営がはじめられた。
時代は弥生時代から古墳時代へと移行し、畿内では豪族間でさらに統合が進んで、大和王権と呼ぶ有力豪族の連合体が形成された。
大和王権は、朝鮮半島の百済・伽耶や中国に使節を送るなどして交流を深め、進んだ技術や文化を取り入れることによりカを強め、地方を支配するための体制づくりを進めたとされる。王権のもとで、豪族に臣・連などの姓が与えられ同族集団毎に組織された。中でも有力な蘇我氏や葛城氏には大臣、物部氏や大伴氏には大連の姓、また、地方の豪族に対しては直や君などの姓を与え、国造や県主に任命して、かれらの勢力下にある土地や人民の支配を認めていたと考えられている。
このような中で最も勢力を伸ばしたのが蘇我氏で、この蘇我氏の専横に危機感をもった中大兄皇子と中臣鎌足は、大化元年(645)蘇我氏を滅ぼし、政治改革に着手した。これが有名な大化改新である。大臣と大連を廃止して左・右大臣をおき、地方には評(後に郡)を設置した。
白雑6年(660)日本と深い関係にあった朝鮮半島の百済が、唐と連合した新羅に滅ばされ、派遣した救援軍は天智2年(663)白村江の戦いで大敗した。これにより、唐の大軍が日本海をわたって進攻して来るのではないかという危機感から、天皇を中心とする中央集権体制への移行を急いだとされる。それは、唐の支配制度にならって、律(刑罰法)と令(行政・訴訟法)という二つの法を国制の基本において、官僚機構と地方行政組織を整えた。大宝元年(701)大宝律令が制定され、翌年施行されてはじめて律令体制の確立を迎えたのである。
その後、和銅3年(710)には、政治の中心が奈良の平城京に移され奈良時代を迎えた。そして、延暦13年(794)に桓武天皇によって都が京都の平安京に移され、貴族中心の宮廷政治が繰り広げられた。以後鎌倉幕府開設までの約400年間を平安時代という。
- 【史料にみる古代都留郡】

- 現在、郡内地域は南・北都留郡に分離しているが、これは明治11年(1878)の郡区町村編制法により、南・北都留郡が設置されて以降のことである。それ以前は、一体の地域として、都留郡が設置されてきた。
この都留郡は、律令体制下の甲斐国の地方組織として、山梨、八代、巨麻と共に置かれていたことが『廷喜式』や『和名類聚抄』に認められる。
『延喜式』は、廷書5年(905)に藤原時平、忠平が醍醐天皇の命により編纂に着手し、延長5年(927)に完成した律令格の施行細則である式を集大成したものである。この中の民部上には全国の国名、等級(大・上・中・下)、所管の郡名、都からの距離による区分(近国・中国・遠国)が記載されている。
- 甲斐国上管
- 山梨 八代 巨麻 都留 (『延喜式』巻22 民部上)
『和名類聚抄』は、わが国最古の分類体漢和辞典であり、承平5年(935)醍醐天皇の皇女勤子内親王の依頼を受けた源順によって編纂され、略本10巻と広本20巻がある。広本は略本に国郡部、郷里部を加えられたものとされる。
- 都留郡
- 相模 古郡 福地 多良 賀美 征茂 都留(『和名類聚抄』国郡部)
これにより都留郡には7郷が置かれ、桂川下流域から配置されていたことがわかる。
7郷の比定地は、下記の通りである。
- 相 模
- 南都留郡秋山村、道志村とする説(『甲斐名勝志』)と神奈川県津久井郡とする説(『大日本地名辞典』)がある。
- 古 郡
- 上野原町付近とされ、牛倉明神の棟札に「古郡上野原村」とあり、また、中世には古郡氏の居館が置かれていた。郷名は、都留郡の郡家がもと置かれていたことによる。
- 福 地
- 大月市の柳川町から富浜町及び猿橋町にかけての地域とされ、富浜町鳥沢に「福地権現」があり、梁川町綱之上小松明神の棟札に「福地郷綱之上村」と記されているという。
- 多 良
- 後の田原郷で、都留市域が中心とされる。現在も、田原の地名が残り、田原滝もある。
- 賀 美
- 郷名は桂川の上流に位置することによる。都留市十日市場付近から西桂町、富士吉田市一帯が郷域とされる。
- 征 茂
- 北都留郡丹波山村・小菅村地方とする説(『甲斐国志』)と、上郷に対する下郷とし大月市大月付近とする説(『甲斐名勝志』)があり、後者が有力とされる。
- 都 留
- 上野原町の西部及び南部が郷域とされ、鶴川、鶴島などは郷名の通称とされる。
- 【詳しく知りたい人】
- 都留市史 通史編 1992 都留市史編纂委員会
- 【都留郡名の由来】
- 郡名となったつるの意味には、川の激流に面する地や、古代朝鮮語の原野などの意味があるといわれている。また、平安時代になると、つるの音が鶴を連想させ、遠い甲斐にある延命長寿のめでたい鶴の郡として、和歌に詠まれるようにもなった。
- 【詳しく知りたい人】
- 都留市史 通史編 1992 都留市史編纂委員会
![]()
![]()
